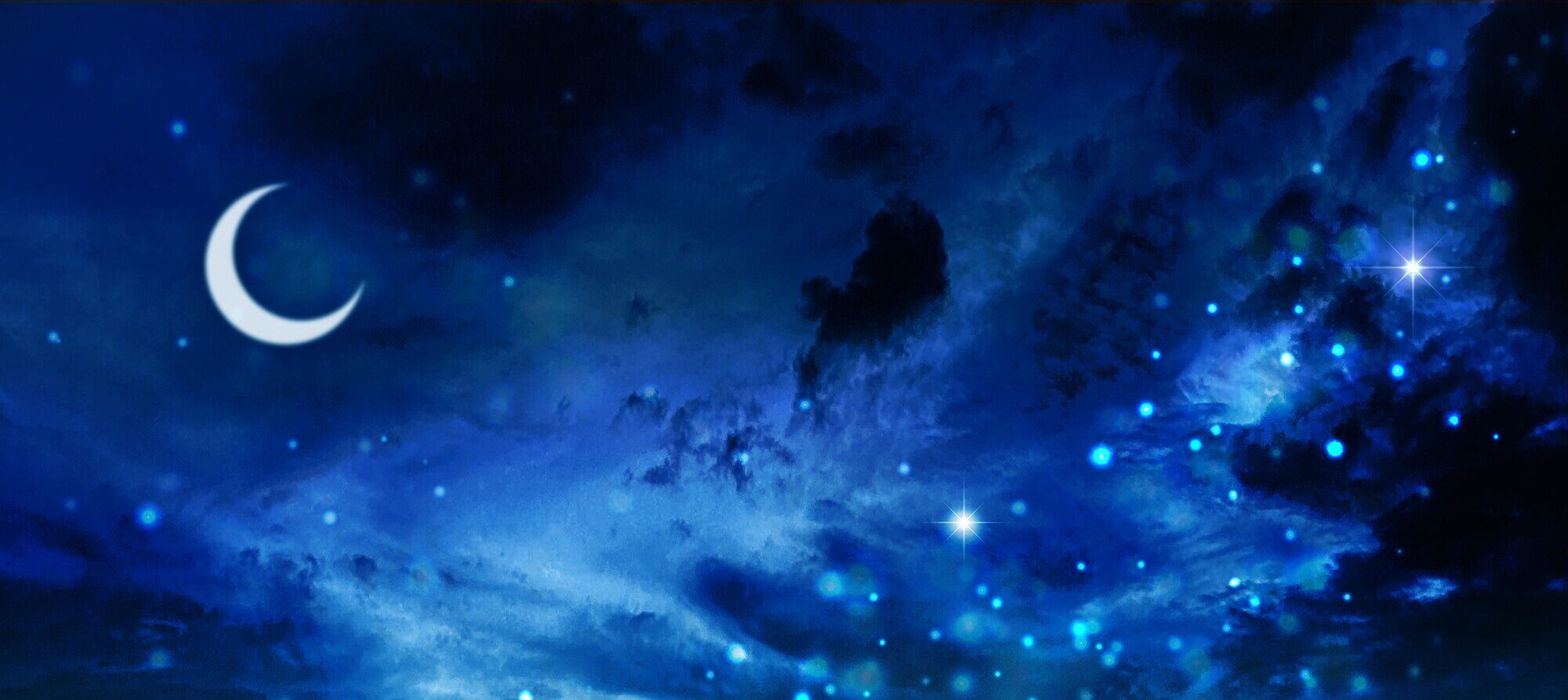市販のドッグフードには、人間が食べる食品では使えない原材料や添加物が配合されている場合があります。背景には、ペットフードが人間の食品と同等の厳格な基準では管理されていない現状があります。本記事では、原材料表示の読み方から「無添加」表示の落とし穴、注意すべき添加物、そして「人が食べても安全(ヒューマングレード)」なフードの見分け方まで、飼い主が知っておきたい要点をわかりやすく解説します。
目次
ペットフードの規制はなぜ緩い?—人間食品との基準差
人間の食品は食品衛生法等で厳格に管理されていますが、ペットフードは同等基準ではありません。2009年施行のペットフード安全法により一定の基準はできたものの、保存料や着色料、香料などの使用は比較的認められやすいのが現状です。このため、長期保存や見た目・嗜好性の向上を目的とした人工添加物や、品質が不明確な低コスト原料が配合されるケースがあります。
要注意の原材料:「肉副産物」「肉骨粉」「〜ミール」を読み解く
原材料欄をチェックすると、「肉副産物」「肉骨粉」「ミートミール/チキンミール」などの用語を見かけます。これらは一見“肉”ですが、実態は次のとおりです。
肉副産物
臓器、骨、軟骨、血液、羽根など人の食用にしない部位を含む総称。栄養価や品質の安定性にばらつきがあり、トレーサビリティも不明確になりがちです。
肉骨粉
家畜の骨や内臓等を高温で処理し粉末化した原料。動物種・部位の特定が曖昧な場合が多く、品質が読み取りにくいのが難点です。
ミール(ミートミール/チキンミール等)
肉や内臓等を乾燥・粉末化したもの。名称に“肉”が付いても副産物を含むことが少なくありません。コスト調整に使われやすく、主原料として多用される製品は注意が必要です。
「無添加」表示の落とし穴—表示義務の盲点
パッケージに大きく「無添加」と書かれていても、完全に添加物ゼロとは限りません。日本の表示制度では、原材料の仕入れ・加工段階で使われた添加物など、最終製品に直接添加していない成分は表示対象外となることがあります。そのため、ラベル上は無添加でも、実際には見えない添加物が残存している可能性があります。
避けたい添加物の例とリスク
一般的なエコノミータイプに見られる代表例をまとめました。長期的な摂取は皮膚トラブル・肝負担・消化不良などにつながる懸念があります。
| 区分 | 例 | 懸念されるリスク |
|---|---|---|
| 防腐剤 | ソルビン酸K、プロピオン酸Na | 肝機能への負担、アレルギー反応 |
| 酸化防止剤 | BHA、BHT、エトキシキン | 発がん性等の指摘(長期摂取に注意) |
| 着色料 | 赤色・黄色・青色◯号 | 栄養価なし。嗜好性演出のみ |
| 香料・甘味料 | 合成香料、グリセリン、糖類 | 食いつき依存、肥満・下痢の一因 |
安全なドッグフードの選び方チェックリスト
次のポイントをパッケージ裏面で確認しましょう。
- 主原料が明確な肉・魚:先頭に「チキン」「ラム」「サーモン」など具体名。「肉類」「家禽ミート」「副産物」といった曖昧表記は回避。
- 添加物の合理性:酸化防止はミックストコフェロール(ビタミンE)やローズマリー等の天然系が望ましい。
- 賞味期限と鮮度設計:製造から1年以内目安。開封後1か月で使い切れるサイズ・小分け包装だと酸化対策◎。
- 製造情報の透明性:製造国・原材料原産地・工場や管理体制の明記。
- 栄養基準適合:総合栄養食の表示、AAFCO/FEDIAF基準準拠など。
なぜ「人が食べても安全」が基準になるのか
人の食品は国際的にも厳格な基準で管理されています。ヒューマングレード(人間用同等の原料・衛生管理)を掲げるフードは、原料・工程・保存の妥当性が検証されやすく、犬にとっても安全性が高い選択肢です。体格の小さい犬は化学物質の影響を受けやすいため、人の基準以上の視点で選ぶことが理にかなっています。
まとめ—パッケージより“中身”を見る習慣を
- 規制の差により、添加物・低品質原料が使われがちなのが現状。
- 肉副産物/肉骨粉/〜ミールなどの曖昧・包括的表記は要注意。
- 「無添加」表示でも、表示義務の範囲外で添加物が残存する可能性。
- 人が食べても安全(ヒューマングレード)、主原料が明確な肉、天然系酸化防止、透明性の高い製品を選ぶ。
大切な家族の健康は、毎日のごはんから。今日から裏面表示を丁寧に確認し、“安全で中身の良い一袋”を選びましょう。
※本記事は一般的な情報に基づくガイドです。個体差がありますので、フード変更時の不調(軟便・嘔吐・かゆみ・急な体重変動等)が続く場合は、必ず獣医師にご相談ください。